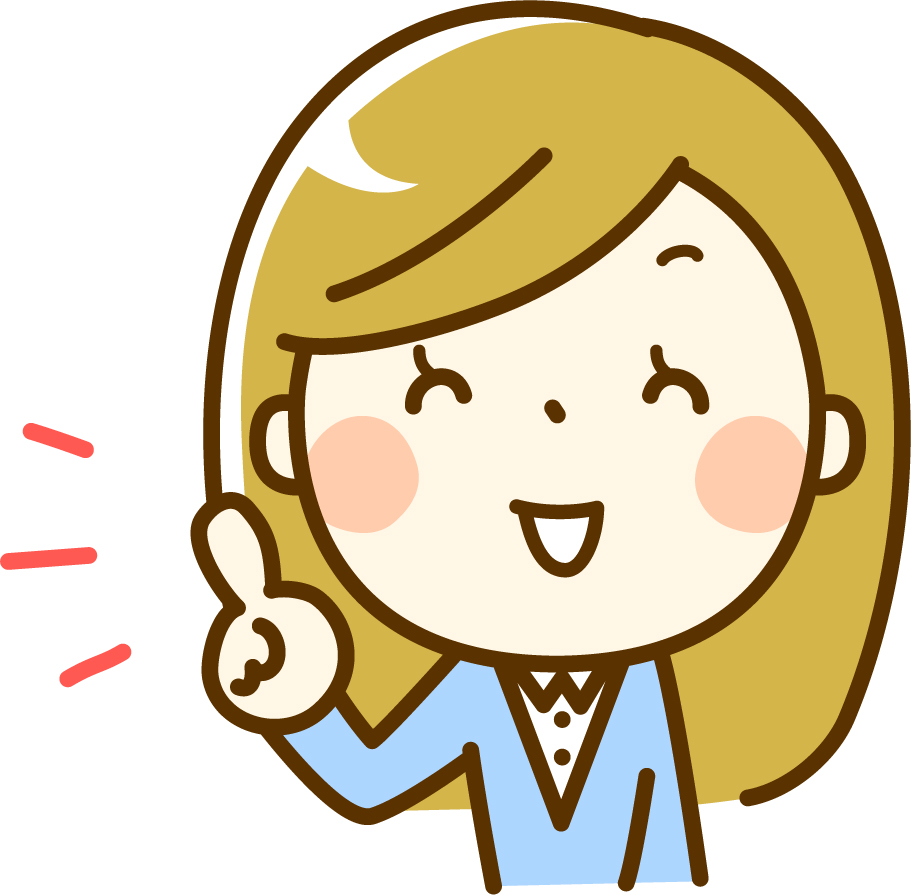当サイトにはプロモーション広告が含まれております。
土鍋を買ったらすぐ使いたいのに、何やら使う前に下準備がいると知って急に土鍋を使うのが億劫になりますよね。
でも、新しい土鍋をすぐに使える方法があるんですよ!それは、土鍋で作る最初の調理をお粥にすることです。
お粥を作ると、下準備である”土鍋にある目には見えない小さな穴を塞ぐ”ことができます。
そしてお粥も同時に食べられるので、実に一石二鳥なんです!
お粥を作ることで水漏れしないし、強度を増して割れにくくなるんです。
この記事では、
- すぐに土鍋を使いたい時のお粥の作り方
- お粥以外で目止めをする方法
- 土鍋を長持ちさせる4つのポイント
について書いています。
お気に入りの土鍋を買ったら、お粥を作ることから始めて長く愛用してくださいね。
すぐに土鍋を使いたいならお粥を作る【目止め完了までの手順】

新しい土鍋をすぐに使いたい時は、最初の料理をお粥にしましょう。
ここで作るお粥は、必ず炊いたお米(ごはん)を使うこと
お米からお粥を作ってしまうと時間がかかってしまい、その間に土鍋が水を吸収しすぎて割れてしまうからです。
お粥で目止めをする場合の手順を見ていきましょう。
- 手順①土鍋を洗う&水漏れしないかチェック
- 手順②お粥を作る
- 手順③火を止めて十分に冷ます
- 手順④土鍋の中身を取り除いて洗う
- 手順⑤土鍋を完全に乾かす
手順①土鍋を洗う&水漏れしないかチェック
新しい土鍋に水を入れて10分ほど待つ。
水が漏れていなければスポンジで軽く水洗いしてから乾かす。(水漏れしていたら不良品なので、お店で取り替えてもらいましょう。)
土鍋を洗ったら、水滴を布巾で拭き取って十分に乾かしましょう。
見た目には濡れていなくても、乾ききっていない場合があります。
洗剤は土鍋に吸収されるので原則使わないこと。
手順②お粥を作る
お粥を食べる場合
- 土鍋に8分目まで水を入れ、ごはんを水の1/3~1/2ほど入れる。(4~5人用9号鍋の場合 お茶碗2~2.5杯分ぐらい)
- 火をつける前にご飯を軽くほぐす。
- 弱火で蓋をせずに1時間ほど炊く。(塩などの味つけはしないこと)


残ったお粥に水を再び8分目まで入れ、弱火で炊きます。
トータルで1時間ほど炊けば完了です。
もちろん最後まで炊き終わってから食べることもできます。
お粥を食べない場合
お粥を食べる時との違いは、ごはんの量を少なくするだけなんです。
- 土鍋に8分目まで水を入れ、ごはんを水の1/5以上入れる。(4~5人用9号鍋の場合 お茶碗1杯分ぐらい)水の代わりにお米のとぎ汁を使うとよりでんぷんの効果が出ます。
- 火をつける前にご飯を軽くほぐす。
- 弱火で1時間ほど蓋をせずに炊く。
水が蒸発したらその分だけ水を加えます。
吹きこぼれないようにときどきかき混ぜましょう。
手順③火を止めて十分に冷ます
土鍋が自然に冷めていくのを待つ。
大きな土鍋だと冷めるまでに数時間かかりますが、その間にじっくりと糊が浸透して土鍋の強度が上がります。
手順④土鍋の中身を取り除いて洗う
土鍋の表面を傷つけないようにスポンジで水洗いする。(洗剤は使わない)
金属製のたわしだとコーティングを傷つけてしまい、そこから汁が浸み込んだりひび割れしたりする原因になります。
手順⑤土鍋を完全に乾かす
布巾で水滴を拭き取ったら、底面をつけないようにして完全に乾かす。
生乾きだとカビやニオイの原因になります。
一晩おいたり、天日干しなどして完全に水気をとりましょう。
これで目止めの完成です!
お粥以外で目止めをする方法

すぐに土鍋を使いたい方には、お粥で目止めをする方法を紹介しました。
お粥以外での目止めをする方法もあるので、ご紹介しますね。
- お米のとぎ汁(おかゆよりも目止めの効果は弱い)
- 小麦粉&片栗粉(無洗米しかない人にはおすすめ)
以下の材料を上記の「手順②お粥を作る」の部分に置き換えてくださいね。
お米のとぎ汁
- 土鍋にお米のとぎ汁を8分目まで入れる。
- 蓋をせずに弱火で1時間加熱する。
- 蒸発したらその分量のとぎ汁または水を足す。
とぎ汁も一般的な目止め方法ですが、加熱しても糊状にならないのでお粥に比べると効果は薄いです。
ですが、一般的に多く売られている萬古焼き(ばんこ焼き)という土鍋は、キメが細かいのでお米のとぎ汁でも十分に効果が得られます。
小麦粉&片栗粉
- 水に対して10%の割合で小麦粉または片栗粉を溶いたものを土鍋の8分目まで入れる。
必ず水に溶いて、でんぷん濃度を一定にしましょう。
火にかけてもしばらくは粉が沈殿するので、ドロッとするまではゆっくりかき混ぜましょう。

- 弱火で1時間ほど、蓋をせずに加熱する。
- 蒸発したらその分量の水を足す。
●吹きこぼれに気をつける。かき混ぜたり、さし水を用意しておく。
●片栗粉はドロっとする分効果があるが、こげつきやすいので注意する。
土鍋を長持ちさせる4つのポイント

土鍋の温かみのある風合いは、質の良い手入れでさらに愛着のあるものにしてくれます。
以下のポイントを抑えて、お気に入りの土鍋を長く使いましょう。
- 急な温度変化を与えない
- 洗うときは傷つけない工夫をする
- 完全に乾いてから収納する
- 目の粗い土鍋は定期的に目止めする
急な温度変化を与えない
土鍋に急な温度変化を与えるとひび割れの原因になります。
≪NGな使い方≫
- 土鍋の外側、とくに底部に水を含んだまま火にかけない。
冷えた底面が加熱されて破損の原因になります。土鍋は弱火から始めましょう。
- 空焚きしない。
底面だけが熱くなり割れる恐れがあるので、必ず水やだし汁を入れてから火にかけましょう。とくに早く乾かそうとして空焚きするのは危険です。
- 熱い鍋を水に浸けたりしない。
急な温度変化で割れる恐れがあります。自然に冷めるまで待ちましょう。
洗うときは傷つけない工夫をする
土鍋の内側はスポンジなどの柔らかい素材で洗いましょう。
金属たわしや研磨剤などで洗うと、目止めでコーティングした所が傷ついて剥がれてしまうからです。
土鍋を洗う時は、洗剤を使わずに水で洗うのが原則。
どうしても汚れが気になって洗剤を使う時は、さっと洗い流すようしましょう。
焦げついた場合は、お湯でふやかしてからペットボトルのキャップで焦げをこすると落ちやすい。
完全に乾いてから収納する
土鍋は乾いたように思っても、まだ底の部分に水分を含んでいる場合があります。
その状態で収納すると、カビやにおいがついてしまいます。
鍋底を上にして一晩ぐらいおいてしっかり乾かしましょう。
目の粗い土鍋は定期的に目止をめする
伊賀焼のような目の粗い土鍋は、使い初めにだけでなく定期的に目止めをすることをおすすめします。
1シーズンに1回ぐらいが理想ですが、コーティングが剥がれるとにおい移りするので、においが気になった時も目止めをする目安になります。
目が粗い分、水漏れしやすくにおい移りもしやすいので、年に数回お粥の目止めで強度とコーティングをアップさせましょう。
まとめ
新しい土鍋をすぐに使いたい時は、最初の料理をおかゆにしましょう。
◆目止めの方法
- 【お粥を作る】
お米を多めに入れると、できたお粥を食べつつ同時に目止めもできる。
伊賀焼など目の粗い土鍋はお粥の目止めがおすすめ - 【お米のとぎ汁】
一般的に売られている萬古焼きなどのキメが細かい土鍋で多く使われる。 - 【小麦粉&片栗粉】
水の量に対して10%を溶かして目止めをする。
無洗米でとぎ汁のでない場合に助かる
◆土鍋を長持ちさせる4つのポイント
- 急な温度変化を与えない
- 洗うときは傷つけない工夫をする
- 完全に乾いてから収納する
- 目の粗い土鍋は定期的に目止めする
土鍋は少々手間のかかる調理道具ですが、手間をかけた分愛着が湧きますし、使いこむほどに味わいも出てきますね。
目止めを丁寧に行ったら、手入れもきちんとして、ぜひ長く愛用してくださいね☆